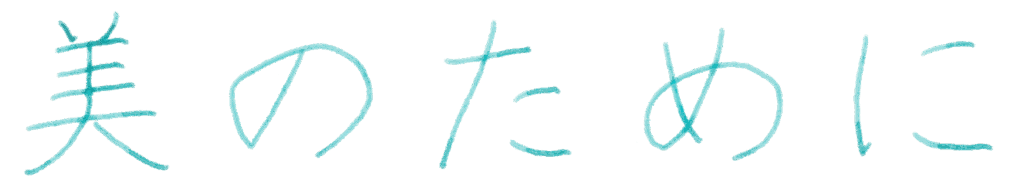梅が満開の公園は曇天で、視界の寒々しさのわりに空気はぬるっとして、裏起毛の上着はほとんど無用だった。今に咲いたばかりの皺ひとつない花々が並ぶ小径で、わたしは本能的に低い枝へ近寄っていて、そこでひとつ息を吐くと、長く長く吸いながら春の浮かれたにおいを期待する。少し道を逸れて永代供養墓の観音菩薩に手を合わせ、口のなかで十句観音経を唱えているとき、傍を散歩する二人の老人が梅の枝に鼻を寄せて目を見合わせ「におい、する?」と尋ね合っていた。わたしたちは満開の梅におびき寄せられて無防備な羽虫にされてしまうが、春のきざしは案外香らなくて、辺りには期待はずれの陰鬱なぬるさがいつまでも滞っている。がらがらの駐車場で待つ愛車は黄色い砂ぼこりに塗れている。そろそろ裏起毛の上着は洗濯して仕舞いたいと思う。
-
水甕
みずがめ座は、ふとした拍子に割れてしまうもののなかに、こぼれたら二度ともどらないものを入れて運んでいます。目の前に水の入った容れ物があるとき、その実体にはいつも影のごとく、割れて中身の飛び散った惨状がつきまといます。みずがめ座のもとへ生まれたからには、そんな容れ物を運ぶ危うさに気づかないふりをして飄々と働き、心中ではどうにでもなってしまえと開きなおるほかありません。わたしたちはしばしば不注意で水をこぼすでしょう。ほかの星座はわたしたちのふるまいにため息をつきますが、みずがめ座の知ったことではありません。だって、みんなため息をつくだけで、ほんとうは水瓶に触れるのすらおそろしくてたまらなくて、誰ひとりとしてみずがめ座の仕事を代わってはくれないのですから。
-
交信のあった年
わけあって私生活が破綻して、いまは諸々を修復の最中にあり、目途が立つまで創作を休んでいる。精神的な余剰が潤沢でないときものを書くのにあまり向かない質だと自覚しているので、ある程度立ち直るまではこのまま大人しく黙っているつもりだ。いわゆる落ちているとき、なのかもしれない。情けない有様だが、それでもどこか悪い気がしないのは、先々月に愛しの児童文学雑誌の投稿欄へ自分の名前が載っているのを見つけたからだ。その小説はまだ生活が滅茶苦茶になる前、夏ごろに書いた。ある孫娘が祖母と連れ立って観音菩薩に祈りを捧げる朝を描いている。雑誌にはただ頁の端にごく小さな文字で載っただけで、べつに作品そのものやあらすじが掲載されたわけでもない。だがわたしは本件に「届くことって、あるんだ!」と心底驚かされた。ボトルレターを拾った衝撃というか、宇宙から暗号を受信した衝撃というか。わたしは自分で書いて、自分で発信するくせに、何らかの反応があることを予期しない。絶望的なまでに内向的で、交信の可能性を信じていないのである。だから人様から何らかの反応があったときは毎度、心底驚いてしまう。今年で同人活動を始めてもう十数年になるというのに。内向的な人間はある意味で幸福な分、孤独の痛みを知らない孤独と生涯付き合ってゆくしかない。小説を書く動機は変えられない。わたしは美しさのために書く。ここまで一度も迷わなかったわけではないけれど、ものを書き始めたときから今までずっと、美のほかのものに従って書けたためしがない。それでも、ときたま書かずにいられなかった美が誰かのもとへ届くことがある。交信は制御できない。どこかへ届いた今年は幸運だった。来年も書く。次に運に恵まれるかは、わからない。それでもわたしが「捨てたもんじゃない」と信じた美しい視界が、いずれかの時間やメディアを経由して思いもよらない誰かにまた届くよう、半ば期待を込めて。
-
生まれつき
生まれたときから桑がありました。わたしはわたしの命に気づいたとき桑を食んでおりました。わたしが桑を食い尽くすとまた桑が降ってきました。だからわたしは桑を食むことしか知らずに生きていたのです。そのうちわたしの傍にみなさんがいたことに気づきました。みなさんもずっと桑を食んでいましたから、わたしはわたしがみなさんと同じ蚕なのだと気づきました。来る日も来る日も桑を食んでいるうちに、わたしたちに桑をくれるひとがいたことに気づきました。わたしはそのひとをおとうさんと呼びました。おとうさんはわたしたちに桑をくれました。でも、いつもおとうさんの隣にいるひとは桑をくれませんでした。わたしは桑をくれないひとのことを、ぼうやと呼びました。ぼうやはときどきわたしたちに触りましたが、桑はくれませんでした。ただおとうさんがわたしたちに桑をくれるのを、じっと見ているだけでした。あるときぼうやは「ぼくにもできそう」と言いました。それからはじめてわたしたちに桑をくれました。わたしもぼうやのくれた桑を食べました。ぼくにもできそう、ってどういうことなのでしょうか。わたしたちは桑を食んでおりましたが、だんだんみなさんの体が白くなってきました。その白がなんだか懐かしいような気がしたとき、おとうさんはわたしたちを桑の葉から落として、どこかへ運んでくれました。みんなで高いところへゆくのがわかりました。なんだかわたしたちはいつか、高いところへゆかなければならないような気がしていました。わたしたちは桑のないところへ運んでもらいましたが、わたしはどうしたらよいのかわからなくて、うずくまっておりました。みなさんのなかには上を向いてから、どこかへ行ってしまう方がいました。わたしもみなさんをまねて上を向いてみると、上にはたくさんの部屋がありました。みなさんは自分の部屋を見つけて、そこで白い糸を吐きました。白い糸に包まれて、みなさんは隠れてしまいました。わたしには自分の部屋がどこにあるかわかりませんでした。どうやって糸を吐けばよいかもわかりませんでした。みなさんがどんどんのぼってゆくので、たくさんあった部屋はほとんど埋まってしまいました。それでもわたしには、自分の部屋のありかも、糸の吐き方も、いつまで経ってもわかりませんでした。みなさんにはどうしてそれがわかったのでしょうか。どうして桑のないところで自分の部屋のありかを見つけられたのでしょうか。どうして吐いたことのない糸で自分を包めたのでしょうか。そのときふと、ぼうやの声を思い出しました。ぼくにもできそう、ってどういうことなのでしょうか。ぼうやは桑に触れたことがあったのでしょうか。そのときようやく、ぼうやも、みなさんも、わたしと同じように、みんながなにも知らずにいたのではないかと、そんな気がしたのです。わたしはなにも知らずとも、天へのぼることができます。なにも知らずとも、白い糸を吐くことができます。なにも知らずとも自分にできることがあるのだと、生まれたときから知っていたのです。わたしはこれからのぼります。白い幕をおろすみなさんの傍を通って、どの方よりも高くのぼってゆきます。おやすみなさい、みなさん、おやすみなさい。わたしは眠りたくなるまで、まだのぼってみようと思います。
【第10回】 私立古賀裕人文学祭「ぼくにもできそう」応募作品
-
拾うのか
朝、いつの間にか真っ赤になっていた街路樹の葉を拾うひとを見かけた。掃くのでなくて、拾うのか。腰をかがめて見つけた形のいい葉がまた一枚、手のひらに重なった。乾いた風に吹かれて間もない葉を選んでいるんじゃないか。集めた葉で絵画かなにか作るつもりだろうか。ともかくわたしは朝に落ち葉を拾うひとと同じ町に住んでいる。