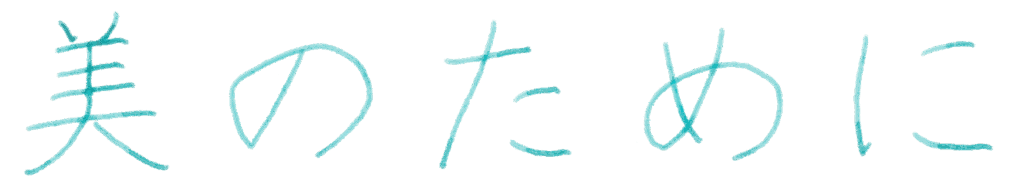青い新しい葉が山いちめんに生い茂った朝のこと。
ひゃくじゅういち、ひゃくじゅうに、ひゃくじゅうさん、ひゃくじゅうよん、ひゃくじゅうご、ひゃくじゅうろく!
苔むした最後の一段を踏みしめて、心のなかで数え切る。太ももが熱をもって痛い。真帆は肩で大きく息をしながら、つつじが鮮やかに咲く参道を抜けて、一足先に観音堂へ向かうばあちゃんの背中を追いかけた。
お山の観音さまの参道には百十六の石段がそびえ立ち、毎朝お参りに来るふたりを待ち構えている。その険しい道のりは、日々の部活動でバスケットコートを全力で駆けまわる真帆にとっても修行のようにつらい。途中で「あと何段あるのかな」なんて考え始めると余計につらいので、今では一段目から百十六段目まで黙々と数をかぞえてやり過ごしている。
それなのにばあちゃんときたら、今朝もすたすたと石段を上ってお堂の前で平然と手を合わせているではないか。どうしてそんなに元気なんだろう。ばあちゃんはほんとうに自分と同じ百十六段を上ってきたのかと、真帆はいつも信じられないような気がするのだった。
少し遅れてばあちゃんの隣に立つと、真帆も同じように手を合わせてまぶたを閉じる。
「観世音、南無仏、與佛有因、與佛有縁、佛法僧縁、常楽我浄、朝念観世音、暮念観世音、念念従心起、念念不離心――」
ばあちゃんが早口で唱えるお経をぼんやりと聞き流す。毎朝、毎朝、なにをお祈りしているのだろう。
その迷いのない声がぴたりと止んだら、そっとまぶたを開ける。剥がれかけた古いお札が黒ずんだ壁や柱のあちこちにひっ付いている。数百年にわたり雨風に耐え、お山の上から真帆たちの町を見守っている観音堂だ。
「じゃ、行きましょーかね」
ばあちゃんがそう言ったら帰りの合図で、今度は百十六の石段を下りてふたりで家まで戻る。
お経を唱え終わるとばあちゃんはあっさりとお山を下りてしまう。雲一つなく晴れていようが、境内の花が満開だろうが、未練のない足取りですたすたと石段を下りて行く。せっかくここまで上ったのに。今日みたいにとびきり見晴らしが良い日はもったいないような気がして、真帆は下りの一段目へ踏み出す瞬間にそっと町を眺めた。
四方を山に囲まれた盆地の端に畑があって、真帆たちの家があって、ご近所さんの家があって、クラスメイトの家があって、知らない人の家があって。さらに向こうには、真帆の通う中学校があって、工場があって、病院があって……。
下りの百十六段はあっという間で、気づけば山門のお地蔵さまを過ぎて、ばあちゃんと隣同士で歩いている。それから真帆は中学校へ行って、ばあちゃんは畑仕事をするのだ。
「年寄りが階段でコケたりなんかしたら危ねぇーからさ、よく見てやってくれよ」
ある日いきなり父に頼まれてからというもの、真帆はばあちゃんの日課である早朝の観音堂へのお参りに毎日欠かさず付き添っている。
こうして大人しく付き添っている理由は、父が珍しく真面目な頼みごとをしてきたからではなく、年老いたばあちゃんを気にかけているからでもない。バスケのための体力づくりにちょうどよさそうだったからだ。
果たして毎朝のお参りの成果なのか、真帆は二年生にあがって間もなく、第二クォーターから試合に出られるようになった。不器用でドリブルのテクニックにはちょっと自信がないけれど、顧問の先生からは「ナイスファイト! 最後までボールを諦めないそのガッツが大事!」とよく褒められる。
もっとバスケが上手くなれるのなら、つらい百十六段の上り下りだって頑張れる。ただ、お父さんには悪いけれど、転ぶどころか平気で先に上って行くばあちゃんのことはちっとも心配なんかしていない。
***
無数の葉に雨粒が打ちつける、むっとした朝のこと。
参道には湿った土のにおいが漂い、雨に濡れた石段がちろちろと光っている。こんな日もばあちゃんはお参りを休まない。傘を片手に少しも怯むことなく一段目を上り始めるばあちゃんに続いて、真帆はいつもより慎重に上り始めた。
いち、に、さん、し、ご、ろく……。
息苦しいほどの湿気でいつも以上に足取りが重い。雨と汗が混じり合ってシャツがじっとりと濡れている。家を出る前にヘアブラシで念入りにとかしつけた前髪は、きっとこの湿度でひどくうねっているだろう。
じゅうさん、じゅうよん、じゅうご……。心のなかで「あーあ、帰りたいな」と弱気な自分の声が聞こえる。その声に呼び寄せられるかのように、幼いころの記憶が浮かんでくる。
ばあちゃんと手をつないでお山の観音さまの石段をゆっくりと上っている。小さい真帆が「のぼる! うえまでのぼるの!」と駄々をこねると、ばあちゃんは手を引いてどこまでも一緒に上った。真帆が石段の半ばで「もうかえる! かえる!」と駄々をこねると、ばあちゃんは「はいはい、かえろ」と手を引いてゆっくりと石段を下りた。
「ばあば、のぼってどこいくの」
帰り道にそう尋ねると、ばあちゃんは「かんのんさまに、おはようってするところ」と教えてくれた。
ふたりでお散歩をするたび、真帆は昔のことをたくさん教えてもらった。ばあちゃんが若いとき織物工場で働いていたこと。お仕事の仲間と一緒にお山の観音さまのお祭りで遊んだこと。毎日休まずに工場へ行ったこと。大きな機械の面倒を見てあげていたこと。ガシャンガシャンと織られていく布がとてもきれいだったこと。一生懸命に働いていたその工場が、ある日おしまいになったこと。
どうしておしまいになってしまったのだろう。
動かない機械の前で立ちすくむばあちゃんの姿が、いつまでも心のなかから消えなかった。小さい真帆には工場がおしまいになったわけが全然わからなくて、かわいそうなばあちゃんのために地面をにらみつけることしかできない。悲しいはずのばあちゃんはなぜか隣で笑っていて、真帆の手を握って静かに揺らしている。
あれ。今、何段目まで上ったんだっけ。
シャツの袖でぬぐってもぬぐっても額から落ちる汗が止まらない。ばあちゃんはやはり真帆よりも一足先に観音堂に辿り着く。雨降りの早朝の境内は普段よりもひっそりとしていた。紫陽花のつぼみがぽつぽつとふくらんでまばらに花が咲き始めている。観音堂の黒ずんだ屋根から絶え間なく雫が落ちる。隣に並んで手を合わせると、ばあちゃんは早口でお経を唱えた。
「観世音、南無仏、與佛有因、與佛有縁、佛法僧縁、常楽我浄、朝念観世音、暮念観世音、念念従心起、念念不離心――」
まぶたを開けてお堂の暗がりと向き合った。薄暗いお堂の奥に、曇天の陽で鈍く光る観音さまが佇んでいる。そのすぐ後ろにある小ぶりな扉は息をひそめるように閉まっていた。
「じゃ、行きましょーかね」
下りの一段目に立つと、山の向こうまで分厚い雨雲に覆われて、真帆にはこの町のすべてが不機嫌に見えた。今日はバトミントン部が体育館を使う日だ。雨で校庭のコートが使えないバスケ部は廊下で筋トレをすることになるだろう。期末テスト前のホームルームでは担任の先生が余計なプレッシャーをかけるから、ここ数日は教室がぴりぴりしている気がする。
「雨のせいでバスケの練習ができないし、しかもテスト前で疲れるし、最近は嫌なことばっかりなんだよね」
山門のお地蔵さまを通り過ぎると、真帆は隣を歩くばあちゃんにそう言い放った。
「あらまあ、大変だ」
「帰ったらシャツを着替えないと。雨の日って面倒くさい。ばあちゃんはお参り、嫌にならないの」
「だってお参りは晴れでも雨でも同じだもの」
「全然同じじゃないよ、雨だと傘をささないといけないし、服も濡れるじゃん」
「傘をさしても、ささなくても、服が濡れても、濡れなくても、観音さまはお山の上で待っているでしょう。だから晴れでも雨でも同じ。いつお参りしても必ずお堂で待っているの。お祈りする人のために」
「ふうん」
真帆はわかったような口調で返事をしたけれど、ほんとうはばあちゃんの言うことがちっともわからない。
でも、晴れの日も雨の日も、コートでバスケができる日もできない日も、テストがある日もない日も、変わらずに目の前の百十六段を上り下りできるとしたら――それはどんな感じなのかなと考えた。そして、毎朝平然とお参りを続けるばあちゃんのことを「のん気でいいなあ」なんて思うのだった。
***
色づいた葉がはらりと落ちる、肌寒い朝のこと。
カーテンを閉め忘れた窓から黄色い朝陽が入る。真帆はいつもより早く目をさました。空高くに薄い雲が浮かんでからっとしている。こんな日はお山の上からいい景色が見られそうだ。てきぱきとジャージに着替えてばあちゃんの待つ居間へ向かう。
ところが、早朝の居間はカーテンが閉まっていて真っ暗だった。「そんなに早く起きちゃったかな」と時計を見やる。ばあちゃんはいつも何時に起きているんだろう。真帆は代わりにカーテンを開けて、しばらく待ってみたけれど、いつまで経ってもばあちゃんは来ない。とうとう真帆がいつも起きる時間になった。
まさか寝坊かな。真帆は和室へばあちゃんの様子を見に行ってみた。
とんとんと襖を叩いてそっと開けると、ちょうど振り向いたばあちゃんと目が合ったのでどきりとした。寝巻のまま眼鏡をかけて文机の前に座っている。なんだ、起きていたのか。ばあちゃんの手元には、ボールペンとチラシを束ねて作ったメモ帖が置いてあった。なにかを書いていたみたいだ。
「あら真帆ちゃんおはよう」
「どうしたん、寝坊?」
不満げに尋ねる真帆に、ばあちゃんは「ちょっとこっち」と手招きすると、一枚のメモを手渡した。
――かんぜーおん。なーむーぶつ。よーぶつうーいん。よーぶつうーえん。ぶっぽうそうえん。じょうらくがーじょう。ちょうねんかんぜーおん。ぼーねんかんぜーおん。ねんねんじゅうしんきー。ねんねんふーりーしん。
そこには、ひらがなでまったく意味のわからない文章が書かれていた。ばあちゃん、一体どうしちゃったんだろう。真帆はぎょっとしてメモを手にしたまま立ちすくんだ。
「かんぜーおん、なーむーぶつ……? あっ!」
声に出して読んでみたら気づいた。これは、ばあちゃんがいつも観音堂で唱えているお経だ。
「今朝はなんだか足が痛くてね。ばあちゃんの代わりにこのお札を観音さまの納札箱に納めてきてちょうだい」
「いいけどさ、それよりも足は大丈夫なの。お父さんたち、起こしてくるよ。早く病院に行って治さなきゃ」
「ううん、そんなに急ぐほどじゃあないんだよ。悪いけれどお参り、お願いね」
真帆は「わかった、行ってくる」と平気なそぶりで和室を出ると、早足で父母の寝室へ向かった。ジャージのポケットのなかで手書きのお札を握りしめながら。
ひゃくじゅういち、ひゃくじゅうに、ひゃくじゅうさん、ひゃくじゅうよん、ひゃくじゅうご、ひゃくじゅうろく!
その日の百十六段は、少しもつらくなかった。
参道の木々から色づいた葉が落ちて、石段のうえに一枚、また一枚と積もってゆく。ぴちぴち、ちちちちとモズが高く鳴いている。真っ青な冷たい空の下に朝日を浴びて観音堂が立っている。
真帆は大股でお堂へ向かってばあちゃんに託されたお札をポケットから取り出す。立ち止まって大きくひと息吸い込むと、ばあちゃんのまねをしてお経を唱えてみた。
「かんぜーおん、なーむーぶつ、よーぶつうーいん、よーぶつうーえん、ぶっぽうそうえん、じょうらくがーじょう……」
その声は震えていた。口を出たそばから跡形もなくなりそうなほどに弱々しかった。体育館の天井に勇ましく響きわたる「ナイシュー、もう一本!」のかけ声とはまるで別人だ。ひとりでお祈りの声をあげるためにこんなに勇気がいるなんて知らなかった。
今ここにいる自分が世界じゅうの誰にも気づかれずに消えてしまいそうで、真帆は思わずお札を持つ手に力を込める。
「ちょうねんかんぜーおん。ぼーねんかんぜーおん。ねんねんじゅうしんきー。ねんねんふーりーしん……」
長い長いお祈りの時間がようやく終わる。真帆はばあちゃんに言われたとおりお札を箱に納めた。そして、薄暗いお堂に佇む観音さまに向かって、もう一度手を合わせた。
「明日また、ばあちゃんと一緒にお参りできますように」
「百十六段」ミツキ・ミイコ
『飛ぶ教室』 第72回作品募集 短編小説部門 一次選考通過作
第57回埼玉文芸賞 児童文学部門 佳作